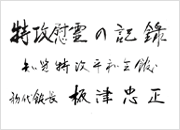自分を見つめ直せる場所
<聞き手>板津さんは陸軍特別攻撃隊の語り部として、戦後全国を駆け回って活動を続けてこられました。お顔の血色もよく、とてもお元気そうですが、おいくつになりますか。
<板津>七十九歳です。昔風に言いますと傘寿を迎えましたが、いまも戦争当時から全然目方が変わっていないんですよ。もう健康そのものです。少しでも長生きをして、散っていった仲間のことを語り続けなければ、という使命感があるもんで、それだけ体には気をつけているから。タバコは吸わないし、酒も一滴も飲まない。
<聞き手>あぁ、ずっと節制をされて。
<板津>飲まなくてもいい血色をしているでしょう(笑)。まぁ、自分なりの努力もありますが、やっぱりこういう活動をしてきたこともあってか、亡くなった人たちの御霊が私を守ってくださっている。そういう感じがしますね。この人たちを守らんことにはいかんと、私の家族まで守ってくださっているような気がします。
<聞き手>いまはこの名古屋を拠点にご活動を。
<板津>もともと名古屋の生まれなんです。鹿児島の知覧特攻平和会館で館長を務めていた時には、単身で向こうに住み込んでいました。そのまま骨を埋める気でいましたが、やりかけていたご遺族捜し、遺品捜しに専念するために地元に戻り、以来家内と二人暮らしです。東へ行くにも西へ行くにも、名古屋のほうが動きやすいですからね。 平和会館のほうはいまは顧問という立場で、年に数回、大きな行事がある時に行っています。この三月には、十四歳と十八歳の孫を連れて行ってきました。私がいくら元気でも、いつまでも生きているわけじゃない。次の世代に大切なことをしっかりと語り伝えておかないといけませんからね。
<聞き手>いま知覧の平和会館は、来場者が引きも切らないそうですね。
<板津>この間行った知人もね、「まぁ、知覧の混んだこと、混んだこと」とびっくりされていました。いま知覧には、年間七十万人もの方が訪れています。人口わずか一万四千人のあの町にですよ。景気の低迷でよその観光地はちょっと下火になっていますが、知覧は逆に伸びる一方なんです。 昭和五十九年に、いまの平和会館の前身の特攻遺品館ができた当時は、見向きもされませんでした。特に学校にはね。日教組の偏見で、戦争に関する全ての記録を抹殺することが平和維持につながる、という考えで学校教育が進められてきたからです。 遺品館を造った当時、知覧に来たある校長先生とお話ししたことがあるんです。実はその方は昔パイロットだったのですが、遺品館には入ったことがないと。なぜかと聞いたら、「睨まれる」と言うんです。あいつは右翼だとか、特攻を美化するとか、そういうふうに見られるので近寄らないようにしている、というのです。これではいかんと思いましてね。
<聞き手>手応えを感じられるようになったきっかけは?
<板津>その後、鹿児島で千人くらいの校長先生が集まる会があって、そこで特攻隊のことをお話ししたんです。そうしたら、これは平和教育に相応しい内容だ、と非常に高く評価していただきましてね。真っ先に佐賀県の学校が見学に来て、すぐに福岡県のマンモス校も来て、それから鹿児島県内や熊本からもどんどん来るようになりました。いまでは全国から五百校が毎年修学旅行で訪れるようになりました。
<聞き手>若い方たちの反応は?
<板津>最初は物見遊山でガヤガヤ騒ぎながら入ってくるけれど、まず館内に展示してある遺書や最後の手紙が、毛筆の見事な筆跡で書かれているのを見て驚くんです。これを自分たちと同じ年代の若者が書いたのかと。そして、お国のため、肉親のために散っていた彼らのことがわかってくるにつれて、「そんなことがあったのか」「自分たちはこんなことではいけないな」という反省が生まれてくるのです。会館を後にする時には、目を赤く腫らして出てくる人もいますが、心の中は何か清々しい。「もっと時間が欲しい」「また必ず来ます」。そんな言葉を残して帰っていくんです。 これは何も若者ばかりではありません。子どもは子どもなりに、大人は大人なりに、若者は若者なりに、自分を見つめ直す機会を与えられるのが知覧です。誰でも壁にぶつかる時があるでしょう。そういう時、知覧に行くと、何か新しい力がもりもりと湧いてくるような気持ちになるから不思議です。私も向こうにいた時にはね、訪れる人のそういう気持ちに応えたくて、一所懸命説明をしました。全館を案内すると四十分かかり、体力も相当消耗するのですが、やり終えたばかりでも、「お願いします」と手を合わされると、疲れも吹き飛んでついついやりたくなってね(笑)。
大空への憧れ
<聞き手>館内にある特攻隊員の皆さんの写真には、感極まるものがありますね。
<板津>あの笑顔を見て、皆さん感動されるんです。これから死出の旅路に立つ者が、なぜあそこまで晴れやかな笑顔をみせられるのか。以前、あれは強制的に笑わされた顔だ、という作家もいましたが、強制されてあんな笑顔になるかってことね。自分で笑ってみれば分かることですよね。今の人に当時のことは分からんものですから、疑問に思うことばかりでしょうね。
<聞き手>ご自身も特攻隊員として、写真に雄姿を留めておられますね。
<板津>私は初めからお国のためとか、肉親のためという気持ちが多分に強かったものでね。 私の母の実家が三重県の明野というところで、当時は戦闘機のメッカだったんです。子どもの頃、そこへ行くたびに空中戦の訓練をやっていましてね、「恰好いいな」と空ばかり見上げていました。その思いが年を重ねるたびに募っていって、逓信省の航空機乗員養成所に入ったところ、戦況が逼迫してきて軍に移管され、そこで私は特攻隊へ志願したんです。
<聞き手>志願する人は多かったのですか。
<板津>空への憧れというのは、当時の若者は誰でも持っていたね。一番若い人は十七歳の時に出撃しましたが、そういう人は十三、十四歳ですでに志願して少年飛行兵になっています。これは、高木俊朗さんという当時報道班員をしていた人が書いていましたが、彼らはみんな早く特攻に行きたくて行きたくて、血書志願するんです。だから整列させるとほとんどが手に包帯を巻いていて、「貴様ら、親からもらった体に自分で傷をつけるとは何ごとだ!」とよく雷を落とされいたそうです。 しかし、競争率が非常にきつかったですから、誰でも航空隊に入れたわけじゃないんです。率で言えば五十人に一人、いやもっと大変でした。受かってもさらに適性検査があって、そこで適性に欠ける人がいるんですね。体力はもちろん、特に視力、聴力は絶対的な条件になります。また、飛行機に乗せて飛んでみると、気持ちが悪くなったり、目が回ったりする人もいて、「もういっぺん出直してこい」と戻されてしまう人もいる。難関を越えて、晴れてパイロットになる時の気持ちは、男冥利に尽きるのひと言でしたね。
<聞き手>やはり入隊後の訓練も厳しい?
<板津>そりゃ厳しかった。生半可なことでは一人前のパイロットにはなれませんからね。よく、「離陸さえすれば後は体当たりするだけだから、簡単なものだ」と、無茶苦茶なことを言う人もいたけれども、そういうわけにはいかんですよ。宙返りや横転などの特殊飛行、空中戦、夜間飛行、射撃と、一切合切やってすべて身につけた者だけが特攻に行ったんです。 幸い私は、小学時代から跳び箱や器械体操の類は群を抜いてうまかったから、パイロットには適していたように思いました。
家族への思いをしたためて
<聞き手>出撃前の心境というのは?
<板津>厳しい訓練の間に部隊が編成され、知覧に行きます。知覧に行けば普通は一泊か二泊で飛び立ちますから、もうウンもスンもないんです。そこであまり長居をしていると、まぁ悪い言葉で言えば、里心がつくというのかな、本人はまったくそう思わなくても、周りが心配するわけです。 その短い滞在期間に、地元の人々から受けた厚情は計り知れませんね。死出の旅路に立つ直前だけに、その親切がいっそう心に染みるんです。中でも、知覧基地の近くにあった富屋旅館の女将の鳥浜トメさんは、特攻隊員たちから“特攻おばさん”と母のように慕われていました。
<聞き手>あぁ、“特攻おばさん”ですか。
<板津>そりゃあ面倒見のいい人でした。もう人が困っていると黙って見とれないのね。後で聞いたところでは、当時トメさんは、着物を質に入れてまで隊員たちをもてなしたそうです。憲兵に睨まれてまでも隊員たちに愛情を注いでくれたんです。 いよいよ出撃の直前ともなれば、各々の思いを、家族への手紙や辞世の句として残しました。私はそれらをほとんど諳んじでいるんですよ。あれこれ説明するよりも、そうした絶筆を直接ご紹介したほうが、出撃前の気持ちはよく分かると思います。
<聞き手>一つ二つご紹介ください。
<板津>これは宮城県の相花信夫少尉、十八歳が、継母である母親に宛てて書いた絶筆です。
「母上、お元気ですか。長い間本当にありがとうございました。我六歳のときより、育ててくだされた母。継母とはいえ、この種の女にあるがごとき不祥事は一度たりとてなく、慈しみ育ててくだされし母。ありがたい母、尊い母。俺は幸福だった。その母上に対して、ついに最後まで『お母さん』と呼ばざりし俺。幾度か呼ばんとしたが、なんと意志薄弱な俺だったろう。母上お許しください。さぞさびしかったでしょう。いまこそ大声で呼ばせていただきます。お母さん、お母さん、お母さんと」
この遺書を、継母であるお母さんがどんな気持ちで読まれたか、察するに余りあると思うんですよね。
それから、愛知県の久野正信大尉は、全文カタカナで遺書を書かれました。五歳と二歳の二人のお子さんがいらして、きっと一日でも早く父親の心情を伝えたいと思われて、小学校低学年で習うカタカナで書かれたのでしょう。
「正憲、紀代子へ。父ハスガタコソミエザルモ、イツデモオマエタチヲミテイル。ヨクオカアサンノイヒツケヲマモッテ、オカアサンニシンパイヲカケナイヨウニシナサイ。ソシテオオキクナッタレバ、ヂブンノスキナミチニススミ、リッパナニッポンヂンニナルコトデス。ヒトノオトウサンヲウラヤンデハイケマセンヨ。『マサノリ』『キヨコ』ノオトウサンハ、カミサマニナッテフタリヲヂットミテヰマス。フタリナカヨクベンキョウシテ、オカアサンノシゴトヲテツダイナサイ。オトウサンハ『マサノリ』『キヨコ』ノオウマニハナレマセンデシタケレドモフタリナカヨクシナサイヨ」云々と。(>片仮名の遺言)
<聞き手>ご遺族への思いが切々と伝わってきます。板津さんの出撃は?
<板津>昭和二十年五月二十八日、同じ部隊の隊員と一緒に、別れの水杯を交わして出撃しました。名誉この上もなし、という心境ですね。これで一人前になった。お国のため、家族のためになるんだという満足感でいっぱいでした。あのような体験ができたということは、人生にとって非常にプラスであったと思っています。
生きていることを忘れるために
<板津>ところが、私が乗った飛行機は、途中でエンジンが止まってしまって島の海岸に不時着し、機体はひっくり返った。しかし火も出ず、無傷で知覧に戻ることになったのです。
<聞き手>どんなお気持ちでしたか。
<板津>慙愧に堪えず、生きているということがこれほど辛いと思ったことはなかった。 私たちは靖国神社に当然入るものだと思っていて、出撃前に皆とこう言い交わしていたんです。 「生まれた時は別々でも、死ぬ時は一緒だ。それぞれに出撃して、見事志を遂げた後は、靖国神社の鳥居の所に集まって一緒に中に入ろう」 隊の仲間はみんな先に行ってしまった。なのに当然死ななきゃいかんやつが、行きとるということ。自分一人のうのうと生きとるのが耐えられんので、早く飛行機をくれ、出撃命令をくれって毎日司令部に押しかけては何度も何度もせっついた。そのたびに、「待て、待て」と押しとどめられたけれども、待てないんです。寝とれないんです。 ようやくのことで出撃命令をもらって喜んだのもつかの間、出撃の日は土砂降りの雨。あの年は本当によく雨が降りました。結局六月下旬に沖縄が陥落し、特攻作戦は中止。私は本土決戦要因として知覧に留まりましたが、そのまま終戦を迎えることになりました。

板津忠正氏と鳥浜トメさん
<聞き手>再び出撃することなく・・・・・・。
<板津>死が当然であった特攻隊員が、生き残ったことの精神の呵責がどれほどのものか。これは体験した者でないとわからんでしょうね・・・・・・。あの時故障さえしなければ。やり切れない思いに、何度眠れぬ夜を過ごしたか。 生き残った申し訳なさから、私は復員後すぐに自分の隊のご遺族を捜し歩きました。皆さんに謝りたかったのです。正直言って、最初は怖かった。「なんでおまえだけ生きて帰ってきたのか!」と責められるような気がしてね。ところが皆さん、「よく訪ねてきてくれた」と、わが子が帰ってきたかのように喜んでくれました。
<聞き手>あぁ、わが子を迎えるように。
<板津>当時は、特攻に行くことを家族に知らせる隊員はほとんどいませんでした。言えば悲しむでしょう。だから家族のもとには、ある日突然戦死の通知だけが来る。まったくの蚊帳の外です。自分の息子や兄弟が、いったいどこから飛んでいって、どういうふうに最期を遂げたのか。それを知りたいと思うのは、肉親の情として当然なことです。それを私が代わりに伝えることで、非常に喜ばれたのです。 その後私は、ご遺族捜しで日本中を行脚するのですが、最初はそんな大それたことなど夢にも思っていませんでした。だけどご遺族の方の喜ばれる姿を見るたびに、自分は特攻隊の事を伝えるために生かされたんじゃないだろうか、と思うようになったんです。 だけど、終戦直後は残念ながら駐留軍がいて動けない。私はその間に名古屋市役所に就職しましたが、いつか機会を見て、と思い続けていました。そして昭和四十八年頃から駐留軍が本国へ帰り始めたのを機に、全特攻隊員千三十七人のご遺族捜しを始めたのです。
<聞き手>うまく捜し出すことはできましたか。
<板津>一人見つけるだけでも並大抵じゃなかった。というのは、駐留軍が入ってきた時に、特攻隊が恨まれて、家族に害が及ぶのではないか、と勝手に解釈して、特攻隊員の名前や出身地など、一切の記録が処分されてしまっていたからです。 幸い、復員局の業務部というところで作ったらしい芳名簿が、四十八年に手に入りました。何度もコピーしたもので、不鮮明なところも多かったんですが、とにかくそれを手がかりに、毎日毎日手紙を書いたんです。返事をくださった方には知覧や万世の写真を送り、それをきっかけに親しくなって、貴重な遺書、遺影、絶筆を送ってくださる方も出てくるようになりました。 残念ながら、宛先人不在で戻ってくるものも多かったですけれどもね。ですから、各地の古老を訪ねては、「こういうパイロットはいなかったか」と、訪ね歩きながら、だんだん狭めて捜し歩いたのです。 役所にもよく足を運びましたが、まともに頼んだのでは、プライバシー保護と一蹴されて終わりです。だけど私は、名古屋市役所で区画整理をやっていた関係で、簡単に引き下がらないような知識があった。戸籍簿は閲覧できないけれども、土地台帳は第三者でも閲覧できて、それが手がかりになることがよくあったんです。
<聞き手>お仕事が遺族捜しの大きな力にもなったのですね。
<板津>そうですね。区画整理とういうのは、もともと建っていた建物や土地を整理して、新たに道路などの公共用地を確保するわけですから、もともとそこにいた人はおもしろいはずない。特に私は、“無く子も黙る駅裏”と言われていた名古屋駅の駅裏を担当していました。そこは外国人やヤクザまがいの人たちに占拠されて巨大な闇市となっていましてね。そこで測量をやっている時に、ピストルを突きつけられて脅されたことだってあります。しかし、私はひるまなかった。
<聞き手>逃げずに立ち向かわれた。
<板津>やはり特攻隊にいたことが、ものすごく力になりましたね。同時に、生きている事を忘れたいがために、夢中で仕事に打ち込んでいたんです。
捜し抜いた千三十七人の遺影
<聞き手>その後、ご遺族捜しの進捗は?
<板津>最初は仕事を抱えながら、土日を利用して近隣を回り、だんだんと範囲を広げていきました。ご遺族にお会いして当時の様子を伝え、遺影をカメラに収め、遺書や遺品をお借りしました。しかし、そのやり方ではとても追いつかない。早く収集しなければ、資料が散逸してしまうという焦りがありました。そこで五十四年、定年を待たずに市役所を辞めて遺族捜しに専念しました。自家用車を運転して走りに走りました。三年で十万㌔、四十日間で六千㌔走ったこともあるんですよ。
<聞き手>大変なご苦労でしたね。
<板津>不思議なことにね、旅先でびっくりするような偶然が必ず起きるんです。この人に会わせるために、見えない何かが指令を出しているんだな、と感じることが再三ありましてね。 例えば、愛知県のご遺族の方々の中に、どうしても見つからない人が一人いた。たまたま愛知県の図書館長の皆さんに講演をした時に、なんとその甥御さんがいらっしゃったんです。 カナダのバンクーバーへ行った時、フェリーの中で一緒に行った人とたまたま知覧の話をしておったら、前に座っていた女の人が振り向いて、「いまのは知覧のお話ですか」とおっしゃってね。そこに一緒にいたご主人が、捜していたご遺族だったんです。 また、別々の伝でお願いしてあった遺影が、五年も経ってまったく同じ日に同時に郵送されてくる、という奇跡のような偶然もありました。
<聞き手>その後、遺品館に入られますね。
<板津>ご遺族捜しが一段落したところで特攻遺品館の館長に迎えられました。しかし、新館設立当時はまだ三百八十四人分の遺影が空白だったんです。館長をしながらあと百三人まで追い込んだんですが、その空白の部分が気になって仕方がない。周辺の同じ隊の遺影からは「早く空白を埋めてくれなければ、俺たちは寂しい」と語りかけられているようで、いたたまれんようになってきたのです。 自分もだんだん年をとっていくし、死ぬまでになんとかすべてやり終えなければ、と思いましてね。結局館長を辞したいと申し出たのです。 そんな私の心の支えは、特攻おばさんのトメさんでした。挫けそうになると「あんたが生き残ったんは、特攻隊にことを語り残す使命があったからなんじゃないの」と励ましてくれました。なんとかそのトメさんが生きているうちに、全員の遺影を集めるぞ、と頑張りました。それがおばさんへの、知覧へのご恩返しと考えていたのです。
<聞き手>その願いは叶えられましたか。
<板津>残念ながら、平成三年にトメさんがお亡くなりになった時は、あと三名だったんですよ。悔しくってねぇ・・・・・・。結局、平成七年にようやく千三十七人全員の遺影が揃ったのです。
<聞き手>よくぞ初志を貫徹されましたね。
<板津>誰にも言えなかったものね。人に言ったって、物好きでやっているだけだとか、勝手なことを言われるだけで。でも急がないと、貴重な資料が散逸してしまう。逸る気持ちにせき立てられるように走り続けてきました。
ただ思わるる国の行く末
<聞き手>遺族捜しを終えた後は、どのような気持ちでご活動を?
<板津>晴れやかな気持ちで旅立った特攻隊員が、ただ気がかりだったのは、自分たちが死んだ後で日本がどうなっていくのか、ということでした。 こんな辞世の句があります。 「国のため捨てる命は惜しからでただ思わるる国の行く末」 「風に散る花の我が身はいとわねど心にかかる日の本の末」 私は、神社などへお参りする時は、日本の現状をずっと報告してきました。亡くなった人たちの御霊に「日本はいまこうなっています」と。かつては、「日本もいまでは世界第二位の経済大国にまで発展しました。若い人たちもいい車に乗って青春を謳歌しています。とてもいい世の中になりました」と誇らしげに報告していました。 ところが最近は、報告するのが心苦しい時があります。子が親を殺したり、親が子を殺したり、非常に説明しづらいことばかりですからね。こうした諸々の問題の元凶は、家庭の躾にあると私は思っています。
<聞き手>あぁ、家庭の躾ですか。
<板津>戦後、われわれは国を立て直すために働け、働けで脇目も振らずに突き進んできました。ところがその間に、最も肝心な家庭の躾が疎かになってしまい、そこから波及していろんな問題が起きてきているのだと思います。 いっぺん悪くなったものは、それが元に戻るまでにはその三倍の時間がかかると私は思います。ですから、戦後六十年で失ったものは、簡単には取り戻せないでしょう。 幸いここへ来て「これではいかん」という人が増えてきて、学校からの講演依頼が増えたり、知覧特攻平和会館への来場者が増えています。 特攻隊員たちは皆、平和を望んでやまなかった。生き残った私は、彼らの語り部としてやっていく以外にその方法が思い浮かばなかったから、一途にこれをやり続けたわけです。日本中の人が知覧へ行くようになれば、校内暴力も家庭内暴力も絶対になくなると私は思っています。ですから、少しでも多くの人に知覧に行っていただきたいというのが、私の切なる願いです。
<聞き手>その平和への願い。そして語り続けてきた特攻隊員の思いは、ご自身の心の詩としていつも流れ続けていた。
<板津>そうですね。仲間たちの絶筆や辞世の句は、戦後私の頭の中から片時も離れることはありませんでした。私にとっての人間の詩とも言うべきその言葉を反芻しながら、きょうまで一途に語り部として活動を続けてきたわけです。この頃では、板津さんはいいことをやった、と言われることも多くなったので、少しは生きてきてよかったかな、とも思います。しかし、生と死という百八十度違う運命の隔たりは、どんなことがあっても埋めることはできません。 生き延びてきた負い目は生涯消えることはないでしょう。私は命ある限り、散っていった仲間たちの慰霊に努め、その思いを語り続けていく覚悟です。
2004年(平成16年)5月インタビュー